「いつかは管理職として活躍したい」そんな思いを抱きながらも、周りを見渡すと女性の管理職がほとんどいない——。そんな現実に、漠然とした不安を感じている20代女性は少なくありません。
実際、日本の女性管理職比率は先進国の中でも際立って低く、キャリアを積みたいと考える女性にとって「見えない壁」が存在しているのは事実です。でも、その理由を正しく理解し、適切な対策を講じることで、あなた自身のキャリアの可能性は大きく広がります。
この記事では、女性管理職が少ない理由を企業・社会・個人の3つの視点から詳しく解説し、20代の今だからこそできるキャリア戦略をご紹介します。

日本の女性管理職はどれくらい少ないのか?データで見る現実
まずは、日本における女性管理職の現状を数字で確認してみましょう。
厚生労働省の調査によると、2024年時点で日本の課長相当職以上に占める女性の割合は約12.7%。部長相当職では約8.5%、役員クラスになると約6.2%まで下がります。これは主要先進国の中でも最低水準で、例えばアメリカでは約40%、フランスでは約35%という数字と比較すると、その差は歴然です。
さらに、業界によっても大きな差があります。金融業界や製造業では女性管理職比率が特に低く5%前後にとどまる一方で、医療・福祉業界や小売・サービス業では20%を超えるケースもあります。
「自分の会社でも、確かに女性の上司はほとんど見かけない」そう感じる方も多いのではないでしょうか。この数字は、多くの女性が感じている「キャリアの天井」が統計的にも裏付けられていることを示しています。
女性管理職が少ない3つの理由
では、なぜ日本ではこれほどまでに女性管理職が少ないのでしょうか。その背景には、企業・社会・個人という3つのレベルでの複合的な要因が絡み合っています。
理由1:企業側の構造的な課題
多くの企業では、管理職候補の育成システムそのものに男女間の偏りが存在しています。
評価制度の見えないバイアス
昇進・昇格の判断において、「リーダーシップ」や「マネジメント能力」という評価基準が、実は無意識のうちに男性的な振る舞いを前提にしているケースがあります。例えば、会議で積極的に発言することや、残業をいとわない姿勢が「やる気」の証として評価される文化では、異なるコミュニケーションスタイルを持つ女性が不利になりがちです。
SHEHUBに寄せられた声の中には、「同期の男性社員は入社3年目で主任に昇格したのに、自分は5年目でようやく声がかかった。評価基準がよくわからない」という相談もありました。
育成機会の不均衡
重要なプロジェクトへのアサインや、海外研修などのキャリア開発機会が、男性社員に優先的に与えられる傾向も見られます。「将来的に管理職になる人材」として想定されるのが男性中心であるため、知らず知らずのうちに経験の差が生まれてしまうのです。
「大型案件のリーダーをやってみたいと上司に伝えたら、『責任が重いから大変だよ』と言われて、結局男性の先輩が担当になった」というエピソードは、決して珍しくありません。
長時間労働を前提とした働き方
管理職=長時間労働という固定観念も、女性のキャリアアップを阻む大きな要因です。特に、夜遅くまでの会議や接待が「当たり前」とされる企業文化では、ライフステージの変化を見据える女性にとって管理職が現実的な選択肢に見えにくくなります。
理由2:社会的・文化的な背景
日本社会に根強く残るジェンダー規範も、女性管理職が少ない理由として無視できません。
性別役割分担意識
「男性は仕事、女性は家庭」という伝統的な価値観は、表面上は薄れてきたように見えても、実は職場の至るところに影響を与えています。結婚や出産を控えた女性社員に対して、「そろそろ落ち着きたい時期だろうから」と重要な仕事を任せないケースや、本人の希望を確認せずに「負担の軽い」部署への異動を打診するケースなどがその例です。
SHEHUB利用者の中には、「結婚を機に総合職から一般職への転換を勧められた。自分はキャリアを続けたかったのに」という体験を持つ方もいらっしゃいます。
ライフイベントとキャリアの両立困難
内閣府の調査によると、第一子出産を機に退職する女性の割合は依然として約46%。育児休業制度の整備が進んだとはいえ、復職後のキャリアパスが不透明だったり、時短勤務では管理職候補から外されたりする現実があります。
「復職後、以前と同じ仕事に戻れると思っていたら、サポート業務ばかりになった」という声は、多くの女性が経験する厳しい現実です。
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)
「女性は細やかな気配りが得意だから事務職が向いている」「リーダーシップは男性の方が自然に発揮できる」といった無意識の思い込みは、本人や周囲の人々の意思決定に影響を与えます。こうしたバイアスは、採用・配置・評価のあらゆる場面で作用し、女性のキャリア形成を制約する要因となっています。
理由3:個人の意識や心理的要因
企業や社会の問題だけでなく、女性自身の意識もまた、管理職への道を遠ざけている一因となることがあります。
管理職への消極的なイメージ
「管理職=激務で責任が重い」「プライベートを犠牲にしなければならない」といったネガティブなイメージが先行し、そもそも管理職を目指すことに抵抗を感じる女性は少なくありません。特に、身近にロールモデルとなる女性管理職がいない環境では、具体的なキャリアイメージを描きにくく、「自分には無理かも」と感じてしまうのです。
ある調査では、20代女性社員の約60%が「管理職になりたくない」と回答していますが、その理由の多くが「ワークライフバランスが取れなさそう」「自分に務まる自信がない」というものでした。
自己評価の低さと完璧主義
女性は男性に比べて、自己評価が低くなりがちだという研究結果があります。「まだ自分には能力が足りない」と考え、昇進のチャンスがあっても辞退してしまうケースも。また、「完璧にできないなら引き受けない」という心理が働き、新しい挑戦を避けてしまうこともあります。
「昇格の打診を受けたけど、自分にできるか不安で断ってしまった。今思えばもったいなかったかも」という後悔の声も、SHEHUBには寄せられています。
ロールモデルの不在
身近に「こんな働き方がしたい」と思えるような女性管理職がいないことは、キャリアビジョンを描く上で大きなハンディキャップになります。特に男性管理職ばかりの環境では、「女性が管理職として活躍できるイメージ」を持つことが難しく、自然とキャリアの選択肢を狭めてしまいます。
女性管理職が少ない企業の特徴
女性管理職比率が低い企業には、いくつかの共通する特徴があります。転職やキャリア選択の際の参考にしてください。
- 男性中心の企業文化が根強い:創業から長い歴史を持つ製造業や建設業など、伝統的に男性社員が多い業界では、組織文化そのものが変わりにくい傾向があります。
- 育児支援制度が形骸化している:制度は整っていても、実際に利用しづらい雰囲気がある企業では、女性が長期的にキャリアを継続することが困難です。
- 評価基準が不透明:昇進・昇格の基準が明文化されておらず、上司の主観に左右されやすい企業では、女性が不利になりがちです。
- 長時間労働が常態化している:残業や休日出勤が「やる気の証」とされる文化では、ライフステージの変化に柔軟に対応できる女性が評価されにくくなります。
- 女性社員の採用自体が少ない:そもそも女性社員の採用が少ない企業では、管理職候補となる母数が限られています。
変化の兆し:女性管理職が増えている企業・業界
一方で、近年は女性管理職の登用に積極的に取り組む企業も増えています。
外資系企業
グローバル基準のダイバーシティ方針を持つ外資系企業では、女性管理職比率が30%を超えるケースも珍しくありません。実力主義の評価制度やフレックスタイム・リモートワークなどの柔軟な働き方が整備されており、ライフイベントとキャリアの両立がしやすい環境です。
「日系企業で行き詰まりを感じて外資系企業に転職したら、性別に関係なく実力で評価してもらえて、入社2年で管理職に昇進できた」というSHEHUB利用者の声もあります。
IT・Web業界
比較的新しい業界であるIT・Web業界は、古い企業文化に縛られず、実力と成果で評価される傾向が強いため、女性のキャリアアップもしやすい環境です。リモートワークやフレックス制度も普及しており、働き方の自由度が高いのも特徴です。
ダイバーシティ推進企業
女性活躍推進法に基づき、積極的に女性管理職の登用目標を掲げている企業も増えています。管理職候補の女性向け研修プログラムや、メンター制度、復職支援制度などを整備し、実質的なキャリア支援を行っています。

20代女性が今からできる5つのキャリア戦略
女性管理職が少ない理由を理解した上で、20代の今だからこそできる具体的なキャリア戦略をご紹介します。
1. 自分のキャリアビジョンを明確にする
まずは「自分がどんなキャリアを歩みたいのか」を言語化することが大切です。管理職になりたいのか、専門性を極めたいのか、ワークライフバランスを重視したいのか——正解はありません。大切なのは、周囲の期待や一般論ではなく、自分自身の価値観に基づいて選択することです。
キャリアビジョンが明確になれば、今の会社で実現可能かどうか、何をスキルアップすべきかも見えてきます。
2. 実績とスキルを積み上げる
20代のうちに、できるだけ多様な経験を積むことが重要です。新しいプロジェクトには積極的に手を挙げ、難しい課題にもチャレンジしましょう。失敗を恐れず、そこから学ぶ姿勢が将来の大きな財産になります。
また、自分の強みとなる専門スキルを磨くことも忘れずに。マネジメントスキルだけでなく、データ分析、マーケティング、プロジェクト管理など、市場価値の高いスキルを身につけることで、キャリアの選択肢が広がります。
3. 社内外にネットワークを構築する
ロールモデルとなる女性管理職や、キャリアについて相談できるメンターを見つけることは、自分の可能性を広げる大きな力になります。社内に適切な人がいない場合は、社外のコミュニティやセミナーに参加するのも良い方法です。
「同じ業界で働く女性のコミュニティに参加したことで、自分の視野が広がり、転職という選択肢にも前向きになれた」というSHEHUB会員の方もいらっしゃいます。
4. 自分の市場価値を定期的に確認する
今の会社だけが世界のすべてではありません。定期的に転職市場での自分の価値を確認することで、客観的な視点を持つことができます。転職エージェントに相談してみたり、他社の求人情報をチェックしたりすることで、「今の環境が自分にとって本当に最適か」を見極めることができます。
必ずしも転職する必要はありませんが、「いざとなれば他の選択肢もある」という安心感は、今の仕事にも良い影響を与えます。
5. 柔軟なキャリアプランを持つ
ライフステージの変化に合わせて、キャリアプランは柔軟に見直すことが大切です。「30歳までに管理職になる」といった硬直的な目標ではなく、「5年後には○○のスキルを身につけている」「将来的には△△な働き方をしている」といった、プロセスと方向性を重視した目標設定がおすすめです。
大切なのは、どんな状況でも自分らしいキャリアを歩み続けることです。
女性管理職を目指す人が選ぶべき企業の見極め方
将来的に管理職を目指したいと考えるなら、企業選びの段階で以下のポイントをチェックしておきましょう。
- 女性管理職比率と在籍年数:単に「女性管理職がいる」だけでなく、その比率や平均在籍年数を確認しましょう。女性が長く活躍できる環境かどうかの指標になります。
- 評価制度の透明性:昇進・昇格の基準が明文化されており、性別に関わらず公平に評価される仕組みがあるか確認します。
- 育児支援制度の実態:制度の有無だけでなく、実際の取得率や復職率、復職後のキャリアパスについても情報収集しましょう。
- 働き方の柔軟性:リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務など、ライフステージに合わせた働き方の選択肢があるかチェックします。
- 女性向けキャリア支援プログラム:管理職候補向けの研修やメンター制度など、女性のキャリア開発を支援する仕組みがあるかも重要です。
- 企業文化とトップのコミットメント:経営陣がダイバーシティ推進に本気で取り組んでいるか、実際に働く女性社員の声を聞いてみましょう。
これらの情報は、企業の公式サイトや採用ページだけでなく、SHEHUBのような口コミサイトや、転職エージェントを通じて得ることができます。
実際にキャリアアップに成功した女性たちの声
ここでは、SHEHUBエージェントを利用してキャリアアップを実現した女性たちの実例をご紹介します。
Aさん(26歳・営業職)のケース
「前職では営業成績が良くても、『女性だから』という理由で重要顧客を任せてもらえませんでした。SHEHUBエージェントに相談したところ、実力主義の外資系企業を紹介してもらい、転職後わずか1年半で昇格。今では大型案件も担当しています。」
Bさん(28歳・マーケティング職)のケース
「将来のキャリアが見えず、漠然と不安を抱えていました。エージェントのカウンセリングで自分の強みを再確認でき、IT企業のマーケティング部門に転職。女性管理職が多い環境で、自分もそうなりたいと思える先輩に出会えました。」
Cさん(25歳・事務職)のケース
「事務職からキャリアチェンジしたいと考えていましたが、何から始めればいいかわからず。SHEHUBエージェントで丁寧にキャリアプランを一緒に考えてもらい、未経験からカスタマーサクセス職に転職。今は自分の成長を実感できる毎日です。」
よくある質問(FAQ)
女性管理職が少ない理由やキャリアについて、よくいただく質問にお答えします。
- Q1. 管理職になりたくない女性が多いのは本当ですか?
A. 確かに調査では管理職志向が低いという結果が出ていますが、その背景には「管理職=激務」というネガティブなイメージや、ロールモデル不足があります。魅力的な働き方をしている女性管理職が増えれば、志向も変わっていく可能性があります。 - Q2. 女性管理職が多い業界はどこですか?
A. 医療・福祉業界、小売・サービス業、IT・Web業界などで比較的女性管理職が多い傾向があります。また、外資系企業や新興企業も女性の登用に積極的です。 - Q3. 20代のうちにやっておくべきことは?
A. キャリアビジョンを明確にし、実績とスキルを積み上げること、そして社内外のネットワークを構築することが重要です。また、定期的に自分の市場価値を確認し、柔軟なキャリアプランを持つことも大切です。 - Q4. 今の会社で女性管理職が少ない場合、転職すべきですか?
A. 必ずしも転職が答えではありませんが、自分のキャリアビジョンと会社の環境が合わない場合は、選択肢の一つとして検討する価値があります。まずはエージェントに相談して、客観的なアドバイスをもらうのも良いでしょう。 - Q5. 女性管理職が少ない会社を見分ける方法は?
A. 採用ページや企業サイトの女性管理職比率、育児支援制度の実態、評価制度の透明性などをチェックしましょう。また、口コミサイトや転職エージェントから実際の社内環境について情報を得ることも効果的です。
まとめ(Summary)
この記事の重要なポイントをまとめます。
- 日本の女性管理職比率は約12.7%と先進国最低水準:企業・社会・個人の複合的な要因が背景にあります。
- 企業側の課題:評価制度のバイアス、育成機会の不均衡、長時間労働前提の働き方が女性のキャリアアップを阻んでいます。
- 社会的・文化的要因:性別役割分担意識、ライフイベントとの両立困難、無意識の偏見が影響しています。
- 20代からできること:キャリアビジョンの明確化、実績とスキルの積み上げ、ネットワーク構築、市場価値の確認、柔軟なキャリアプランが重要です。
- 企業選びのポイント:女性管理職比率、評価制度の透明性、育児支援の実態、働き方の柔軟性、キャリア支援プログラムをチェックしましょう。
あなたらしいキャリアを実現するために
女性管理職が少ない理由を理解することは、自分のキャリアを戦略的に考えるための第一歩です。企業や社会の構造的な課題がある一方で、それを理由に諦める必要はありません。
大切なのは、自分が本当に望むキャリアを明確にし、それを実現できる環境を選ぶこと。そして、20代という貴重な時期に、できるだけ多くの経験を積み、自分の可能性を広げることです。
もし今の環境で将来が見えづらいと感じているなら、一度立ち止まって自分のキャリアを見つめ直してみませんか。
SHEHUBエージェントでは、女性のキャリアに特化した専門のキャリアアドバイザーが、あなたの悩みや希望に寄り添いながら、最適なキャリアプランをご提案します。「管理職を目指したい」「今の会社で成長できるか不安」「自分に合う環境を見つけたい」——どんな相談でも大丈夫です。
まずは気軽にカウンセリングを受けてみることで、新しい視点や可能性が見えてくるかもしれません。あなたらしいキャリアを実現するための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。


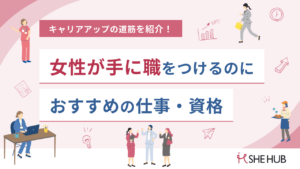
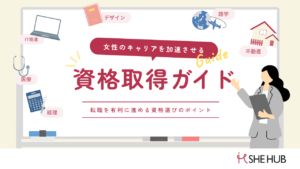

コメント